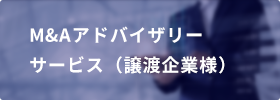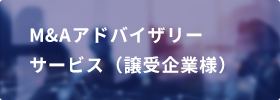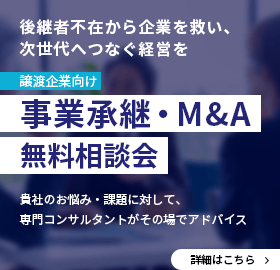M&A情報
M&Aでのデューデリジェンス(DD)とは?
デューデリジェンスの種類と流れを解説
2021.06.01
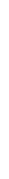
デューデリジェンスとは、M&Aの交渉過程で行われる、買い手企業が売り手企業に対して行う調査のことを言います。
様々な観点からのデューデリジェンスがありますが、デューデリジェンスの対応は売り手オーナーとしては非常に労力のかかるものです。ただし、買い手企業はリスクを見落とさないために必ず行いますので、本コラムでは、デューデリジェンスの種類、流れ等をわかりやすく解説していきます。
デューデリジェンスとは
デューデリジェンス(DD)とは、投資や譲受を行う前に対象企業の詳細な調査・分析を行うプロセスの事を指します。
日本語に訳すと、「当然行われるべき(Due)」「注意、努力(Diligence)」といった意味となり、「デューデリ」と省略される場合や、日本語で「買収監査」と呼ばれる場合もあります。
該当分野に対応する専門家(公認会計士、弁護士、税理士など)が実地調査をすることで資料と実態に差異がないかを徹底的に確認します。
M&Aは高額取引になることが多いため、成功率を上げるために入念に準備を進めましょう。特にM&A対象の価値やリスクはM&A交渉の土台となるため、譲渡側と譲受側の認識を一致させなくてはなりません。そのための準備の一環として重要な流れがデューデリジェンスです。
加えて、デューデリジェンスで得られた知見は買収価格の細部調整や補償条項の設計、さらには統合後のシナジー創出計画にまで直結します。調査範囲や実施タイミングを戦略的に設計することは、無駄なコストを抑えつつ意思決定の精度を高めるうえで不可欠です。近年はITシステムの脆弱性や人的資本の健全性を確認するIT・人事デューデリジェンスの重要性も増しており、企業規模を問わず実施が推奨されています。

デューデリジェンスの目的
デューデリジェンスを行う目的は「リスクの把握」、「リターンの把握」、「スキームや経営方針の決定」の3つが挙げられます。
・リスクの把握
デューデリジェンスを行う第一の目的です。M&A実施の意思決定のため譲受対象企業の問題点や簿外債務など、経営上のリスクを把握します。リスクを確認していない場合、譲受後に不慮の揉め事が起きて予期しない損害を受ける可能性があるため、注意が必要です。
M&A実施可否の最終判断のために小さな問題をもリスクとして顕在化させるのが、デューデリジェンスの役割になります。
・リターンの把握
M&Aでリスクを避けるのは当然のことですが、M&Aとは本来、収益の拡大を目論んで行います。従って、デューデリジェンスのもう1つの大きな目的は、譲受の成果として、どれだけのリターンが見込めるかの把握になります。このリターンとは、単に新事業が加わることでの収益増加だけではなく、既存事業との間でどれだけのシナジー効果があり、それによって、それぞれの事業がさらにどれだけの収益の伸びしろがあるかの予測まで行います。多少のリスクを抱えている企業であったとしても、リターンのほうが大きいものであればM&A成約の可能性はグッと高まるでしょう。また、想定されるリターンの大きさによって、M&A成約時の譲受額も左右されます。
・経営統合スキーム・経営方針の決定
企業経営の観点からすればM&Aの目的は、売買契約の締結ではなく、新たなビジネス展開のスタート地点です。
デューデリジェンスでつかんだ、譲渡側企業のリスクとリターン、さらに既存事業とのシナジー効果、それら全ての情報を用いて、M&A後のビジネススキームや経営方針を定め、実行していくことになります。その意味においても、デューデリジェンスは重要な役割を持っているのです。また、M&Aを実行する場合、譲受側の経営陣には、株主を筆頭とするステークホルダー(利害関係者)への説明責任が生じます。
デューデリジェンスの種類
デューデリジェンスの種類は多岐にわたりますが、良く実施されるものを解説していきます。
・税務デューデリジェンス
過去の申告内容や未払税金を洗い出し、将来発生し得る追徴課税リスクを数値化します。税務署からの調査履歴や更正手続きの有無を確認し、取引スキームの選択方針に反映させることで、買収後のキャッシュフローを安定化させます。
・ITデューデリジェンス
基幹システム・クラウドサービスの利用状況、IT統制の成熟度やサイバー攻撃への備えを点検し、統合時に必要となる投資額を試算します。業務効率を維持するための移行手順やバックアップ体制もデューデリジェンスの重要な論点です。
・人権デューデリジェンス
国連指導原則を踏まえ、強制労働や差別がサプライチェーン内で発生していないか調査します。上場企業だけでなく、中小企業においても海外展開や不動産開発の場面で求められるケースが増加しており、ブランド価値や法的リスク管理に直結します。
・セルサイドデューデリジェンス(ベンダーデューデリジェンス)
売り手が主体となり専門家へ依頼し、自社課題を事前に洗い出す手法です。資料の作成、質問集の準備を先行して行うことにより、買い手の検索工数を削減し、交渉期間の短縮や価格維持に効果を発揮します。弊社でも案件規模を問わず採用が進んでいます。
特に、財務・税務・労務は、株式譲渡スキームの場合、必ずと言ってよいほど調査される事項になります。
事業内容以外の潜在リスク、もしくはコンプライアンス違反の隠蔽などが行われていないかの調査が目的で、会計処理や資産管理が適切に行われているか、M&Aの手法や契約に問題が無いかなどが問われます。
その他、M&A後の事業統合(PMI)をスムーズに行うための、実態把握という側面もあります。

デューデリジェンスの流れと対応方法
デューデリジェンスは、M&Aの交渉過程の一つですが、一般的には、意向表明書の提出もしくは基本合意書の締結を経て、ある1社の買い手企業との独占交渉に入ったタイミングで実施されます。この段階では、自社のおおまかな概要資料は既に相手方に提出しており、資料分析およびトップ面談がなされ、買い手企業との譲渡条件のすり合わせはできている段階と思っていただければと思います。その上で買い手企業に対し、より詳細の資料を開示し、様々な質問に対する回答をして買い手企業のリスク対策をしていくのがデューデリジェンスとなります。
デューデリジェンスに入る段階で、買い手企業から必要資料リストが提示されます。これを、できる限り早く準備し買い手に対して提出をします。その後、資料精査を経て買い手企業・デューデリジェンス委託専門家からのインタビューを受けます。また、実地調査がある場合が多くあります。調査期間は企業の規模や事業内容、業種、資料の提出状況などによって大きく変わりますが、1~2か月程かかるケースもあります。
売り手企業としては、資料の準備や様々な専門家から失礼ともあら探しともとれる質問等を多く受けることになりますので、とても労力のかかることとなります。しかしながら、基本合意書にはデューデリジェンス対応の義務が明記されることが多く、またこのデューデリジェンスに協力し円滑に進めなければ契約締結には至りませんので、アドバイザーの力を借りながらできる限り早く、協力的に進めていくことが肝要です。

デューデリジェンスの期間と費用
デューデリジェンスに要する期間は、およそ1~2か月ほどですが対象企業・事業の規模や業種、調査する範囲などによって2週間で完了するケースもあるなど、場合によって期間は異なります。一般的には企業の規模が大きくなるほど調査する項目が増えるためデューデリジェンスにも時間がかかります。資料の提出など対象企業側の協力を得る必要もあるため、その点も考慮して計画立てる必要があります。
また、費用についても対象企業の事業規模や調査の範囲、依頼する専門家の熟練度によって前後するため一概にいくらと断定は出来ませんが中小企業だと数十万~数百万円、大きい企業や海外の会社だと数百万円~数千万円となっています。
デューデリジェンスを実施する際の注意点
デューデリジェンスを行う際に注意すべき点を4つご紹介します。
1.M&Aの規模、内容に応じて適正な範囲で行う
企業や事業の規模に見合ったデューデリジェンスの実施が必要です。規模に対して、調査範囲が限定的だと、不十分な調査によりリスクを背負う可能性があります。反対に、必要以上に調査範囲を広げて実施すると、M&Aの必要性が問われます。
また、時間の短縮化やコスト軽減を理由に、本来必要な調査を省略する、あるいは、外部専門家に依頼せず自社内の担当者だけで完結しようとすると、重大なリスクを見逃す可能性があります。そのため適正な範囲でデューデリジェンスを行うことが必要です。
2.期間内に優先順位をつけて行う
調査の期間内に必要な情報を探し出せるよう、調査項目に優先順位をつける必要があります。確認すべき調査項目に優先順位をつけておくことで、調査の範囲を広げず、費用と時間の節約が可能です。また、買い手企業側が、M&Aを急いでいたとしても、前述の通り対象企業の協力無くしてデューデリジェンスは実施できません。相手の都合も考慮して、計画立てることが必要です。
3.対象企業は積極的に情報提供を行う
調査される側となる対象企業は、買い手側から請求された資料の提供や、聞き取り調査など、協力姿勢で対応する必要があります。また、あらかじめ認識している自社が抱えるリスクについても、隠さず伝えておくことが重要です。後からリスクの存在が明らかになることで、最悪の場合、M&Aが破談につながる可能性もあるため、両者の信頼関係のためにも、積極的に情報提供を行うことが大切です。
4.情報管理を徹底する
デューデリジェンスでは、買い手企業側が対象企業の機密情報に触れるため、秘密保持契約を締結します。入手した情報の取扱いに細心の注意を払う必要があります。調査のために得た情報をM&A以外で使用できないよう、売り手側は制限をかけ、場合によっては、専門家に開示範囲について助言を求めるのが良いでしょう。
デューデリジェンスを成功させるポイント
デューデリジェンスを成功させるための重要なポイントは以下の3つになります。
1.正確な情報を資料にまとめる
デューデリジェンスで提供する資料はM&Aを検討する際の重要な判断材料になります。譲渡側が提供する情報が正確ではない場合、M&Aの判断資料にできず、デューデリジェンスの目的は達成されません。譲受側の判断次第ではM&A譲受を見送る結果になることもありえるため、客観的なデータを提供するためにも正確な情報をまとめるようにしましょう。
2.顧問税理士などに協力してもらう
デューデリジェンスは該当分野の専門知識が必要になります。税務や法務などの専門的知識がなければ、調査・分析作業を満足に実施できず、価値・リスクを洗い出すこともできません。もし専門家にあてがない場合は、顧問税理士などに相談することをおすすめします。中小企業の場合は日常の税務処理で税理士と顧問契約していることが多いので、会社の内情もよく把握しています。特に税理士は財務・税務・事業などのデューデリジェンスに幅広く対応できるので、相談先の候補として最適です。
3.M&Aの専門家に相談する
デューデリジェンスは、M&Aの専門家に相談する方法も有効です。完全に外部の専門家であれば客観性も高く保てるので、デューデリジェンスで収集する情報の信憑性を高める効果も期待できます。また、M&A譲受後の事業展開も見据えることが大切です。M&Aの専門家であれば、統合プロセスは得意分野なので具体性のある計画を立案できます。
以上3つのポイントを意識して後悔のないデューデリジェンスを行いましょう。

デューデリジェンスに関するよくある質問
続いて、デューデリジェンスの際に、よくいただく質問をまとめております。
ぜひ、参考としてご覧ください。
1. デューデリジェンスの費用は誰が支払うのか
通例、費用は調査を依頼する買い手側が支払います。理由は判断に必要な情報を自ら取得する行為であるためです。ただし入札形式などで売り手が事前に調査を済ませ、報告書を各候補へ配布する方式をとることもあります。
その場合は売り手が最初に支払い、最終的に成約価格へ上乗せするケースや、買い手が後日按分して精算するケースなど、契約で定めた方法に従います。
2. 規模に関わらずM&Aではデューデリジェンスが必要か
金額の大小よりも「見逃せないリスクが潜んでいるか」が重要です。中小規模のM&Aでも、簿外債務、許認可の欠落、未払残業代などが後から判明すれば損害は一気に膨らみます。調査範囲や深度を絞り込むことでコストと時間は抑えられるため、最低限の確認でも実施しておくほうが安全です。
3. デューデリジェンスでリスクが見つかったら取引はどうなるのか
リスクの種類と修復可能性に応じて選択肢が変わります。金額換算できる問題なら価格調整や補償条項の追加で合意する例が多数です。
改善策が明確で実行に時間を要する場合は、クロージング後の条件付き支払い(アーンアウト)を組み込む場合もあります。一方、法令違反や訴訟が深刻で是正の目途が立たない場合には、交渉を打ち切る決断もあり得ます。
まとめ
デューデリジェンスはM&Aを成功させるうえで欠かせない工程です。M&A対象の適正な価値を調査することは、M&A後の経営を安定化させることにもつながるため、計画的に臨む必要があります。デューデリジェンスを円滑に進行するためには専門的な知識や入念な準備が必要です。その際は、外部の専門家に相談し、協力を仰ぐことをおすすめします。
タナベコンサルティングでは、年間にわたり大企業から中堅・中小企業まで約200業種、17,000社以上の経営コンサルティングをしてきた経験をもとに最適なデューデリジェンスのサポートができます。
M&Aをご検討の企業様はタナベコンサルティングにご相談ください。

小野 樹
M&Aコンサルティング事業部
ゼネラルパートナー
金融機関や会計事務所とパートナーシップを築き、後継者を育成する企画や取引先企業が抱える経営課題とコンサルティングソリューションをマッチングするアライアンス事業を推進。M&A部門の事業化、仕組みづくり、商品開発、実績づくりを行い、大手企業のバイサイド支援から中小・個人企業のセルサイド支援まで幅広い実績を持つ。
- 主な実績
-
- 大手生活品メーカーの同業買収に関するバイサイドFA
- 中小システム開発会社のM&Aアドバイザリー
- 中堅建設業の同業買収に関してのデューデリジェンス
- 地場ゼネコンのM&A戦略構築支援
- リサイクル関連会社の企業買収に関するセカンドアドバイザリー
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など