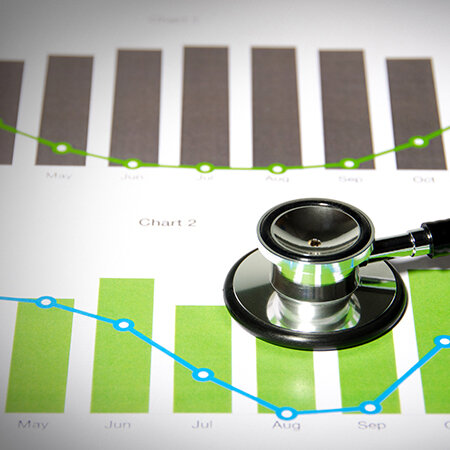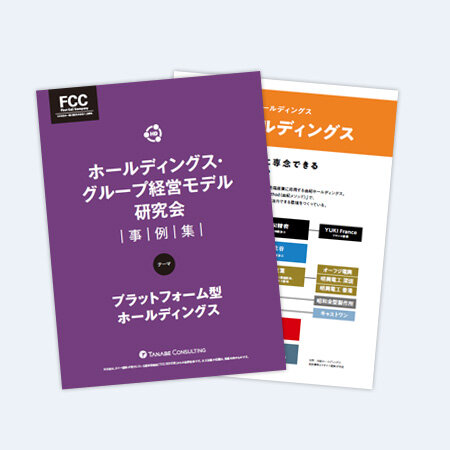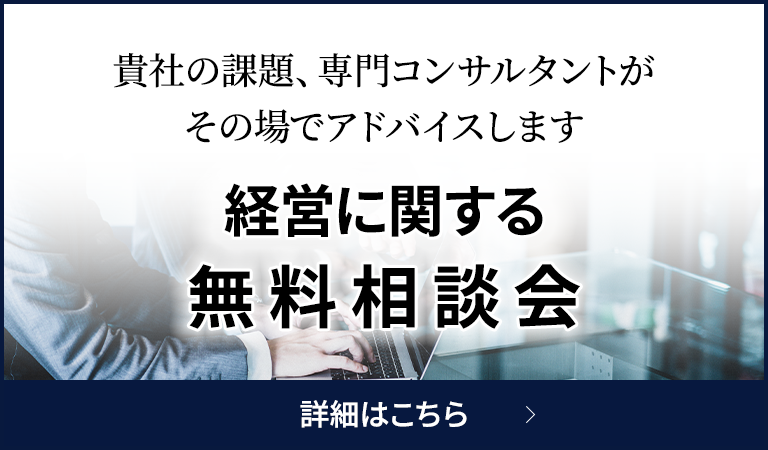企業価値とは?
意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上

閉じる
従来、日本の"優良企業"とは、長年かけて自己資本を蓄積し、キャッシュを貯め込む経営により自己資本が厚く、キャッシュリッチな企業とされてきました。しかし近年、これまでの財務価値の向上に加えて、環境負荷の低減、社会貢献活動、ガバナンスの強化など、ステークホルダーから求められることは多様化しています。このような背景から、資本効率を高めて成長投資を積極的に行う持続可能な経営を推進する企業が増加していると言えます。
したがって、企業価値の要素である株主価値や市場評価、ブランド力、顧客満足度、従業員のエンゲージメントなどが相互に関連し合い、持続可能な成長を支える基盤をつくることが重要となります。
本コラムでは、企業価値の定義、時価総額と事業価値の違い、評価方法について解説します。
1.企業価値の定義
企業の目的は中長期的な企業価値向上と持続的な成長を実現することであり、株主だけでなく社会・顧客・取引先・従業員などの全てのステークホルダーにとっての価値を最大化することが求められます。企業価値は株主や投資家などステークホルダーにとって重要な指標であり、企業の経済的健全性や成長可能性を測るための基準となります。
企業価値とは将来にわたって生み出す経済的な価値と社会的な価値の総和を示す指標です。主にその企業の将来の収益力や資産の価値などの財務価値と、ブランド力、顧客基盤、従業員の能力、社会的責任などの非財務価値を総合的に評価したものです。そのため、企業価値を高めるには売上高や利益率、投資効率などの財務資本と知的資本・製造資本・人的資本・社会関係資本・自然資本からなる非財務資本の両方からのアプローチが必要ですが、具体的には、資本構成の見直しや研究開発への積極投資によるイノベーション、社員研修などの人材投資、社会的責任の遂行などの長期的視点の取り組みが挙げられます。
2.時価総額と事業価値との違い
企業の使命は投資家から期待される価値創造活動を行い、株主価値の最大化を図ることにあります。そのためには、企業価値・事業価値・株主価値を明確に定義・区分しそれぞれで価値を高めていくことが重要です。下記にてそれぞれの違いについて解説します。
まず、企業価値とは企業のステークホルダーに対する価値であり企業の現在から将来にかけての収益力を示します。計算式は企業価値=事業価値+非事業用資産となり、将来発生するキャッシュフローを見込んだうえでの現在価値を評価します。
次に、事業価値とは事業から生み出される将来キャッシュフローの合計のため将来の収益力や市場での競争力を示します。そのため、事業価値は企業の資産や負債を考慮に入れつつ事業活動に焦点を当てた評価となります。特に、事業価値は新規事業の評価や事業再編の際に重要となります。
最後に、時価総額は株主に対して、株式市場において上場株式がどれくらいの価値・規模があるかを測るための基準として算出します。計算式は時価総額=株価×発行株数となりますが、株価が短期的な市場参加者の心理状態を反映して動くことに留意する必要があります。したがって、経営者としてはB/Sの改善および将来キャッシュフローの獲得に注力していくことが重要となります。
3.代表的な企業価値の評価方法
企業価値の評価方法はマーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチの3つの切り口で分類されます。
(1)マーケットアプローチ
評価対象会社または評価対象事業の取引を、類似公開会社や類似事業の取引と比較分析することによって、企業価値を算定する方法です。代表的な手法としては「公開している類似会社の株価」と「当該会社のある財務数値との倍率」を算定し、評価対象会社の財務数値に、その倍率を乗じて算定する類似会社比準法があります。
メリットとしては実際の市場取引や同業他社のデータに基づくため客観的かつ業界特性も考慮した評価が比較的容易に可能なことです。
一方でデメリットとしては比較対象となる同業他社の選定が困難であることや中小・中堅企業や新興企業の場合データ入手が困難なことが挙げられます。
(2)インカムアプローチ
将来期待される経済的利益をその利益(キャッシュフロー)が実現するのに見込まれるリスクなどを反映した割引率で現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。代表的な手法としては、将来のキャッシュフローを予測し、加重平均資本コスト(WACC)を使用して現在価値に割り引いて企業価値を算出するディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)や将来の収益を予測し適切な還元率で割り引いて現在価値を求める収益還元法があります。
メリットとしては将来の収益やキャッシュフローに基づくため長期的視点で本質的な価値を反映しやすいことや割引率を設定するため企業のリスクを考慮した評価が可能なことです。
その一方で、デメリットとしては将来予測の不確実性が高いことや割引率の設定において主観的な要素が多く適切な設定が困難なことが挙げられます。
(3)コストアプローチ
資産、負債の価値を直接評価することによって企業価値を算定する方法です。代表的な手法としては企業が保有する資産(流動資産、固定資産など)を評価し、負債を差し引いて純資産を算出する資産評価法や企業が同様の資産を再調達するために必要なコストを基に企業価値を評価する再調達原価法があります。そのため、コストアプローチは決算書である貸借対照表から算出するため中小企業のM&Aで利用されることが多いという特徴があります。
コストアプローチのメリットとしては会社の貸借対照表に記載されている純資産の価値を基に計算するため客観性が高いことです。
その一方、デメリットとしては企業の業績や将来の収益を反映できないことや個別資産および負債の価値算出に時間と費用がかかることが挙げられます。
4.まとめ
本コラムにて、企業は株主の利益を最大化するだけでなく、従業員や顧客、地域社会などのステークホルダーに対しても価値を提供することが求められると解説しました。企業は効率的な資源配分や革新を通じて価値の最大化を図り、企業価値向上のみならず社会全体の価値創造を目指し持続可能な社会の実現に寄与していくことが重要です。
関連記事
-

内部統制の基本理解と解説:成長と信頼を築く、社員一人ひとりの意識改革
- 資本政策・財務戦略
-

中堅・中小企業のホールディングス化は最適か?メリット・デメリットを解説
- ホールディング経営
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト