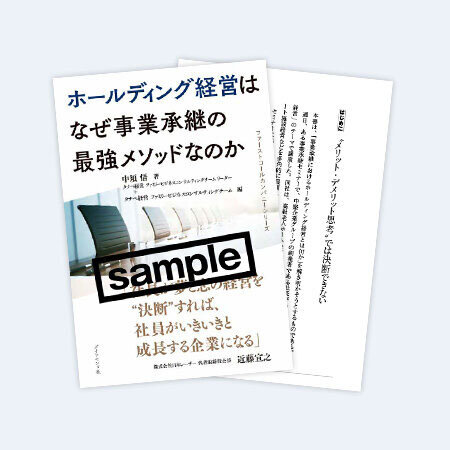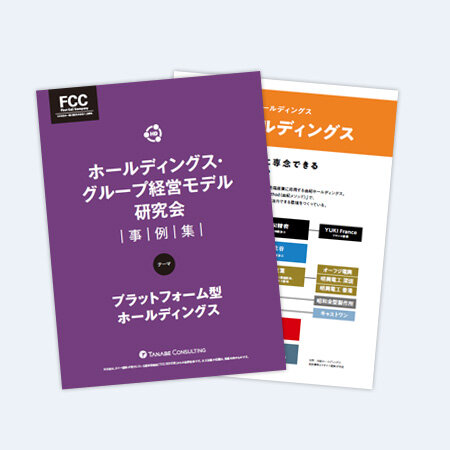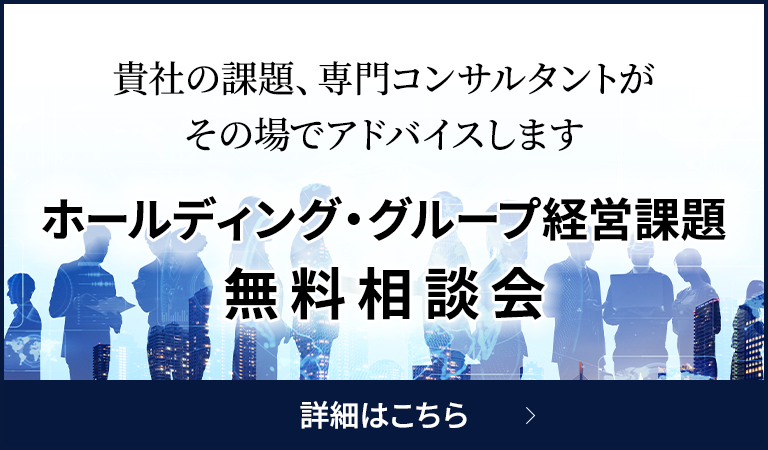中堅・中小企業の
ホールディングス化は最適か?
メリット・デメリットを解説
- ホールディング経営

閉じる
近年、中堅・中小企業がホールディングス化を実施するケースが増加しています。この傾向は、筆者が担当する北陸エリアにおいても顕著に見られます。2020年頃より中堅企業を中心にホールディングス化を実施するケースが増え、その後、中小企業にまで動きが広がっています。ホールディングス化とは、複数の事業会社を統括する持株会社を株式交換や会社分割などの手法を用いて設立し、持株会社がグループ会社の人事や経理機能を統括し、運営する経営形態のことです。ホールディングス化はすべての中小企業にとって最適な選択肢なのでしょうか。本コラムでは、中堅・中小企業がホールディングス化を検討する際の重要性やメリット・デメリットについてご紹介します。
中堅・中小企業がホールディングス化する背景や重要性
事業承継と事業統括の観点
中堅・中小企業では、後継者不足に悩むケースが多く、事業承継が円滑に進まない状況が増えています。近年ではオーナー家以外の人物が後継者となり、事業を引き継ぐ形態が全体の30%を超えるようになりました。そのため、これまでホールディングス化は主に大企業の戦略として認識されてきましたが、資本(オーナー家)と経営(事業責任者)を分離する手段として、中堅・中小企業においてもホールディングス化の有効性が注目されるようになっています。ホールディングス化を行うことで、持株会社が事業資産を管理し、後継者が複数の事業を一括して統括する形が可能になります。これにより、事業承継の負担が軽減され、次世代への移行がよりスムーズになります。
ホールディングス化を検討する狙いは様々です。一般的には、「グループ経営管理の高度化」・「意思決定の迅速化」・「業績責任の明確化」・「ガバナンス強化」などが挙げられます。
特に中堅企業は、成長・発展してきた歴史の中で、高い確率で事業を多角化しています。その場合、事業そのものが異なるため、事業ごとに異なる戦略や運営体制が必要ですが、ひとつの会社の枠の中では、中期経営計画や単年度方針展開など、整合性を図ることが難しくなってきます。
そのため、中堅・中小企業が複数の事業を展開する場合、ホールディング経営体制を構築しておくと、各事業会社が独自の経営判断を行えるようになり、グループ全体の柔軟性が向上します。また、事業ごとに独立性を持たせることが可能となり、リスク分散や効率的な運営が期待できます。
中堅・中小企業がホールディングス化するメリット
1.事業承継の円滑化
中堅・中小企業にとっては、前述の通りホールディングス化は事業承継の観点で特に有効です。持株会社が主に不動産などの資産を管理することにより、後継者が複数の事業を一括して引き継ぐ事業承継が可能になります。また親族などへ事業ごとに責任者を分けていきやすいため、柔軟な事業承継が実現します。
2.経営の効率化
ホールディングス化により、グループ全体の経営戦略を持株会社が統括する形となります。各事業会社は担当する事業の運営に専念でき、経営資源の最適配分が可能となります。また、持株会社が財務や人事などの共通業務を一元管理していけば、間接経費のコスト削減や業務効率化が期待できます。
3.リスク分散
複数の事業会社を設立することで、事業ごとのリスクを分散することができます。例えば、ある事業が業績不振に陥った場合でも、他の事業が好調であればグループ全体の収益の安定性を保つことができます。またある事業会社に信用上の問題が生じた場合でも会社が別であれば、悪影響を低く留め得る可能性が高まります。これにより、経営の持続可能性が向上します。
4.資金調達の多様化
ホールディングス化により、グループ全体の信用力が向上する場合があります。グループ経営という信用の傘のもと、金融機関からの融資や投資家からの資金調達が容易になる可能性があります。場合によっては、事業会社ごとに資金調達を行う運営形態も考えられ、資金の用途を明確化しやすくなります。資金調達機能は持株会社で一本化する、各社ごとに資金使途を明確にして自立型で調達するとしても、いずれにしても資金調達の多様化が期待できます。
5.経営の柔軟性向上
ホールディングス化により、事業会社ごとに独立した経営判断が可能になります。これにより、各事業が市場の変化に応じて、迅速に対応できるようになります。事業会社ごとに異なる戦略を採用することも可能となるので、採用した戦略が市場動向とマッチすれば競争力を高めることができます。
中堅・中小企業がホールディングス化するデメリット
1.組織文化(イズム)の変化と守るべき組織文化(イズム)の両立が難しい
ホールディングス化により、従業員の意識や組織文化(イズム)が変化する可能性があります。特に、事業会社ごとに独立性を持たせる場合、どの程度事業会社に裁量権を持たせるかで、持株会社社員と事業会社社員間の連携が弱まるリスクがあります。定期的な接点を持つ機会を設けるなど、ホールディングス設立時点で、適切なコミュニケーション戦略の設計が必要です。また、M&Aなどで新たにグループインする会社が増加した場合、守るべき組織文化(イズム)を浸透させる伝道師が都度必要となります。事業そのものの可能性を評価し、M&Aを展開した場合は、社風(イズム)が異なることが多く、伝道師は自社の社風(イズム)に馴染んでもらうために、時として鬼軍曹的な役割を担うことができる人材育成が必要です。
2.税務上の課題
ホールディングス化には税務上のデメリットの可能性もあります。ホールディングス設立前の母体会社の会社区分が大会社だった場合、ホールディングス化により、持株会社の事業構造や資産構造の変化によって、株価算定で有利になる可能性が高い大会社の区分維持が困難になる可能性があります。持株会社設立時に大会社の要件を満たすことのできる規模感で持株会社を設立できれば良いですが、3年間は一般的に純資産価額が適用されます。意図しない早期相続が発生した場合、算定株価がアップし思わぬ税負担が生じる可能性があります。持株会社の純資産の拡充や従業員要件を徐々に満たしていけば良いですが、考えておくべきデメリットです。
3.初期コストの増加
ホールディングス化を行うには、持株会社の設立や組織再編に伴うコストが発生します。持株会社に対して多額の不動産の移転を伴う場合には、このコストは多額になります。また、法務手続きや税務対応、専門家への相談費用などが含まれます。特に資金力が限られている企業にとって、これらの初期コストは大きな負担となる可能性があります。
4.管理の複雑化
ホールディングス化により、グループ全体の管理が複雑化する場合があります。持株会社と事業会社の間で意思疎通が不足すると、経営判断の遅れや混乱が生じるリスクがあります。
中堅・中小企業におけるホールディングス化を考える
中堅・中小企業におけるホールディングス化は、昨今の状況においては、事業承継や事業多角化の観点から有効な選択肢となるケースが多く見られます。しかし、単一事業に集中している企業や資金力が限られている企業にとっては、ホールディングス化のメリットが薄いケースもあります。初期コストの発生や管理の複雑化、また必ずしも株価低減につながらないケースもあります。メリット・デメリット双方存在するため、慎重な検討が必要であり、自社にとっての最適解を見つけることが重要です。
中堅・中小企業が持続的な成長を目指すためには、経営戦略の柔軟性と実効性が求められます。ホールディングス化は有効な選択肢のひとつであり、適切に活用することで、企業の未来を切り拓く可能性を秘めています。中堅・中小企業がホールディングス化の選択肢を検討する際、メリットとデメリットを十分に理解し、慎重に判断することをお勧めします。
関連記事
-

内部統制の基本理解と解説:成長と信頼を築く、社員一人ひとりの意識改革
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト