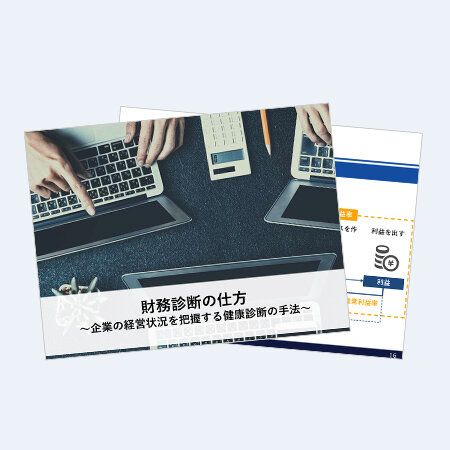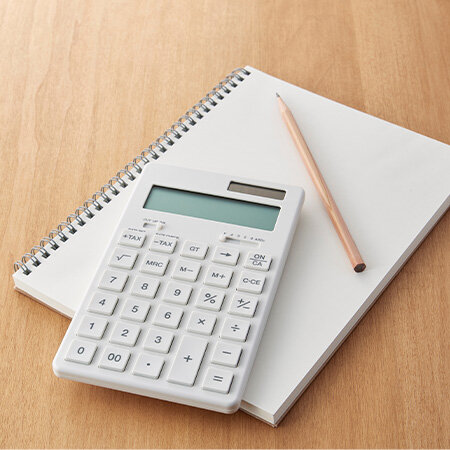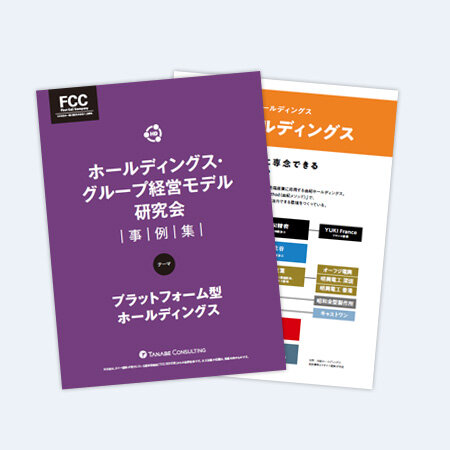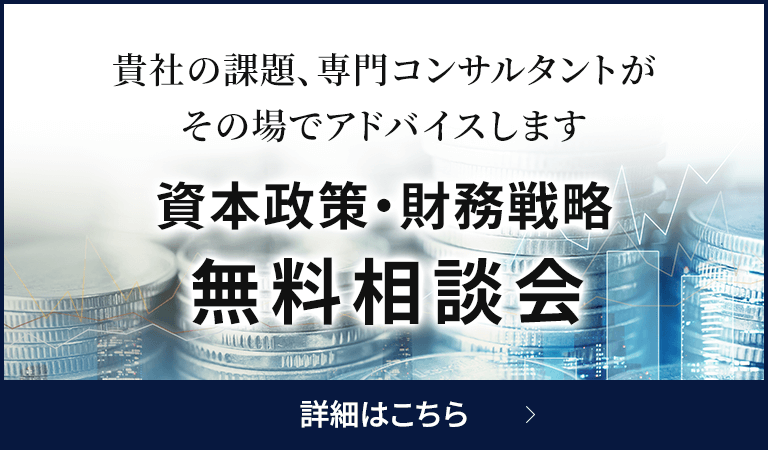ROEとROAの違いをわかりやすく解説|
実務に役立つ財務指標の見方とは
- 資本政策・財務戦略

閉じる
企業の財務状況を評価する際、ROE(自己資本利益率)とROA(総資産利益率)は、経営の効率性や収益性を測るうえで非常に重要な指標です。どちらも「利益をどれだけ効率的に生み出しているか」を示すものですが、評価の視点や意味合いは大きく異なります。
ROEは株主の視点から資本の使い方を評価する指標であり、ROAは企業全体の資産運用効率を測るものです。つまり、同じ「利益率」という言葉を使っていても、見ている対象や、そこから得られる示唆も異なります。
ROEとROAの基本的な定義、それぞれの特徴や使いどころ、実務での活用における注意点を4つの章に分けて整理します。財務分析や経営判断に携わる方々にとって、指標の「読み方」を見直すきっかけとなれば幸いです。
ROEとROAの基本を押さえる
収益性を測る2つの視点
ROE(Return on Equity)は、企業が株主から出資された自己資本を使って、どれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。株主にとっての「投資効率」を測るものであり、資本市場では特に重視される傾向があります。たとえば、ROEが10%であれば、株主が出資した100円に対して10円の利益を生み出していることになります。
一方、ROA(Return on Assets)は、企業が保有する総資産全体を使って、どれだけの利益を生み出しているかを示します。こちらは、企業の経営資源全体をどれだけ有効に活用できているかを評価するための指標です。ROAが高い企業は、資産を無駄なく使って利益を上げていると評価されます。
両者ともに「利益率」を示す指標ですが、ROEは株主資本に対する効率性を表し、ROAは企業全体の資産運用効率を示すため、企業の財務構造や資本政策によって数値の意味合いが大きく変わってきます。
ROE(自己資本利益率)
= 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)
→ 株主資本に対する利益率
ROA(総資産利益率)
= 当期純利益 ÷ 総資産 × 100(%)
→ 総資産に対する利益率
評価軸の違いとその意味
財務構造が数値に与える影響
ROEとROAの違いは、単に計算式の違いにとどまりません。ROEは自己資本を基準にしているため、借入によって自己資本を抑えればROEの数値を高めることが可能です。これは、いわゆる財務レバレッジの効果によるものです。つまり、同じ利益でも自己資本が少なければROEは高くなります。
一方、ROAは総資産を基準にしているため、借入の有無にかかわらず企業全体の資産運用効率をフラットに評価できます。財務構造に左右されにくいため、より保守的な視点から企業の収益性を測ることができます。
この違いは、投資家と経営者の視点の違いにも通じます。投資家は自分の投資に対するリターン(ROE)を重視し、経営者は企業全体の資産運用効率(ROA)を重視する傾向があります。
たとえば、同業種で同規模の企業が2社あった場合、一方は自己資本比率が高く、もう一方は借入を多く活用しているとします。ROEの数値は後者の方が高くなる可能性があります。しかし、ROAで比較すると資産全体の運用効率が見えるため、より実態に近い評価が可能になります。
実務での使い分けと判断軸
目的に応じた指標の選定
ROEとROAは、どちらが優れているというものではなく、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。
たとえば、以下のような場面でROEは有効です。
・株主へのリターンを意識した経営戦略の評価
・株式投資の判断材料としての企業比較
・自己資本の活用効率を把握したいとき
特に上場企業では、ROEが資本市場での評価に直結するため、経営陣がKPIとして重視するケースも少なくありません。投資家からの信頼を得るためにも、ROEの改善は重要な経営課題となります。
一方、ROAは以下のような場面で力を発揮します。
・経営資源全体の運用効率を評価したいとき
・借入依存度の高い企業の健全性を確認する場合
・業界をまたいだ経営効率の比較を行うとき
金融機関や投資ファンドなどは、ROAを通じて企業の本質的な収益力を見極めようとします。特に、設備投資が大きく資産規模が膨らみやすい業種では、ROAの分析が欠かせません。
また、ROEとROAの両方を並べて見ることで、企業の財務戦略やリスクの取り方を読み解くことも可能です。たとえば、ROEが高くROAが低い場合、過度な借入によって資本効率を引き上げている可能性があるため、財務リスクの有無を慎重に見極める必要があります。
<ROE>
活用場面:株主リターンの評価、資本効率の分析
主な利用者:経営陣、投資家
<ROA>
活用場面:経営資源の運用効率、財務健全性の評価
主な利用者:経営者、金融機関
指標の読み方と注意点
数字の裏にある構造を見極める
ROEやROAの数値は、単体で見るだけでは不十分です。たとえば、ROEが高くROAが低い場合は、過度な借入によって資本効率を引き上げている可能性があります。一方、ROE・ROAの両方が高い企業は、資本・資産の両面で効率的な経営がなされていると評価できます。
また、業種によって適切な指標は異なります。金融業や不動産業のように資産規模が大きい業種ではROAが重視され、ITやサービス業のように軽資産型の業種ではROEが重視される傾向があります。
さらに、ROEやROAの数値は、会計上の処理や一時的な要因によっても変動するため、複数年にわたる推移や他の指標との組み合わせで分析することが望ましいでしょう。例えば、営業利益率や自己資本比率とあわせて見ることで、より立体的な財務分析が可能になります。
ROEとROAはそれぞれ異なる視点から企業の実力を測る指標です。どちらか一方に頼るのではなく、両者を組み合わせて分析することで、より立体的で実態に即した経営判断が可能になります。
<ROE>
メリット:株主視点での収益性が明確、資本効率の良し悪しがわかる
デメリット:借入で数値が操作されやすい、財務リスクを見落とす可能性
<ROA>
メリット:企業全体の効率性を評価できる、財務構造に左右されにくい
デメリット:資産評価の影響を受けやすい、株主リターンとの直接的な関係が薄い
関連記事
-

内部統制の基本理解と解説:成長と信頼を築く、社員一人ひとりの意識改革
- 資本政策・財務戦略
-

中堅・中小企業のホールディングス化は最適か?メリット・デメリットを解説
- ホールディング経営
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト